第1回:笑顔の裏にあった誤解──“わかりました”が通じなかった日

「現場で本当にあった外国人材トラブルとその学び」シリーズ
「はい、わかりました」──その言葉を信じた結果、現場で起きたすれ違い。
「昨日の夜勤、Bさんのトイレ誘導がされていなかったみたいです。」
朝の申し送りでその報告がされた瞬間、フロアには静かな緊張が走った。
夜勤を担当していたのは、インドネシア出身の技能実習生・アミさん。
真面目で優しく、利用者にも人気のある職員だ。
普段から「はい、わかりました」と元気よく返事をし、業務への意欲も高い。
しかしその“はい”が、実は「本当に理解した」という意味ではなかったことに、
このとき誰も気づいていなかった。
何度も「わかりました」と言っていたのに…
問題となったのは、夜間の排泄介助の引き継ぎだった。
「Bさん、最近トイレ失敗が増えてるから、0時に一度トイレ誘導お願いね。」
アミさんは、少し不安そうな顔をしつつも「はい、わかりました」と返答。
笑顔を浮かべていたため、引き継いだスタッフも深く確認せず業務を離れた。
翌朝、Bさんのパッドはぐっしょりと濡れており、皮膚に赤みも見られた。
誤解の原因は「言語」ではなく「文化」
後でアミさんに確認したところ、彼女はこう答えた。
「すみません…『誘導』って言葉がよく分かりませんでした。でも、忙しそうだったので聞けませんでした。」
アミさんにとって、“はい”は「話を聞いています」という意味合いで、
必ずしも「理解しました」という確証の表現ではなかった。
また、目上の人に対して「分かりません」と言うことを遠慮しがちな文化背景もあり、
その場では笑顔で応じるしかなかったという。
“わかったつもり”は、現場にとって一番危険
介護の現場では、排泄介助ひとつ取っても、利用者の尊厳や健康に直結する。
「わかっていないまま進める」ことは、重大なトラブルの火種になる。
問題は、“本人も分からないまま進んでしまう”こと、
そして、“周囲もそれに気づけない”ことにある。
今回のような事例は、小さなすれ違いが蓄積されることで、
やがて事故や信頼喪失へとつながってしまう。
学び:確認の習慣が、誤解を防ぐ
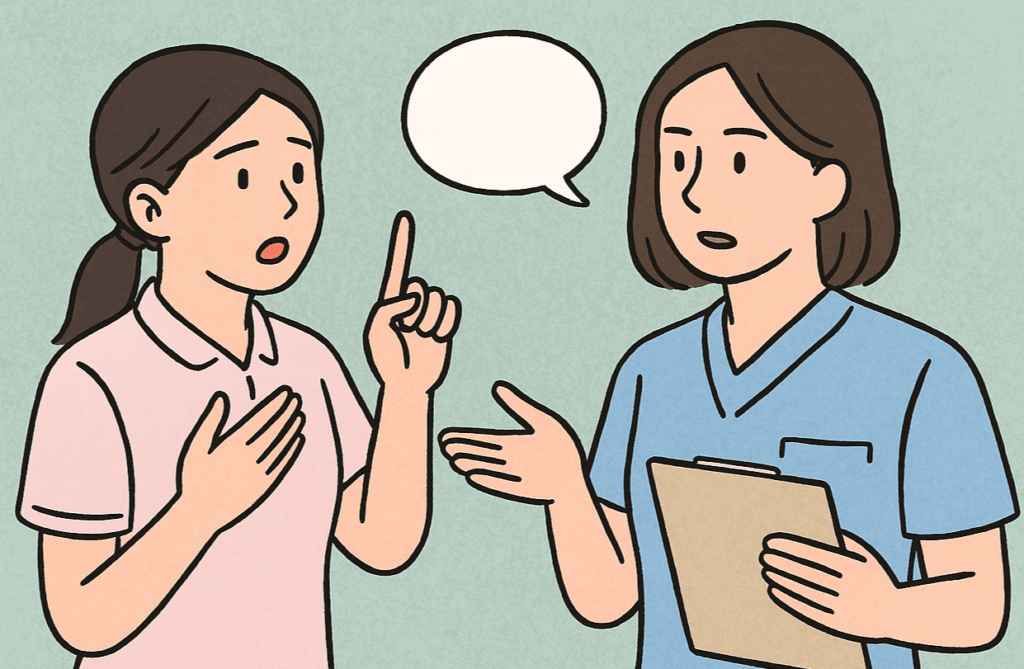
この出来事をきっかけに、施設では次のような取り組みを始めた。
1.「説明してもらえる?」の確認
「わかった?」ではなく、「じゃあこのあと何するか教えて?」という“復唱”の促しによって、本当に理解しているかを確認できるようにした。
2.「質問しやすい空気づくり」
「忙しいから後で」ではなく、1〜2分でも手を止めて「ここまで大丈夫?」と声をかける習慣に。「質問しても良い」という安心感が、誤解を減らす第一歩となる。
3. 図解マニュアルの整備
「誘導」「排泄介助」「声かけ」などを視覚的に説明するツールを作成。
言葉だけでは伝わりにくい概念も、絵や写真で補うことで理解度が上がった。
最後に:笑顔は、わかっているサインじゃない
外国人材は、慣れない環境で頑張ろうとしている。
だからこそ、「わかったふり」や「笑顔の奥にある不安」を、私たちが見逃さないことが重要だ。
「はい、わかりました」という言葉に安心するのではなく、
その先にある“本当の理解”を、共につくっていく。
それが、信頼関係を築き、安全な現場を守る第一歩となる。
近年、介護施設で外国人材の活躍が当たり前になってきた一方で、 次のようなお悩みを耳にすることが増えています。
特定技能外国人支援コスト削減のご提案
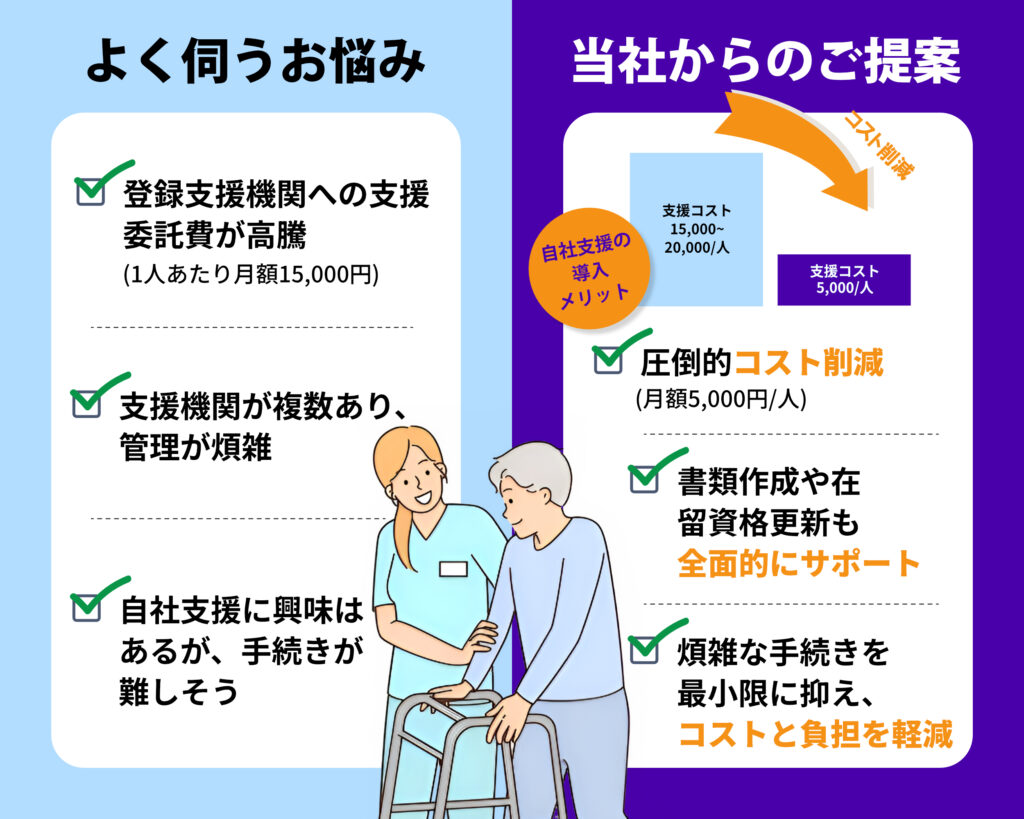
このようなお声に応え、当社では「自社支援」の導入をご提案しております。
まずは、削減効果のシミュレーションや導入事例をご紹介させてください。
オンラインでのご相談も可能です。
