第2回:そりゃ、泣かれるでしょ?──“叱ったつもり”が裏目に出る文化の違い

「現場で本当にあった外国人材トラブルとその学び」シリーズ
「ちゃんとして!」の一言で、心を閉したワケ
「あれ…泣いてる?」
その日、早番のリーダー・佐藤さんは、スタッフルームの隅で目を赤くしてうつむくインドネシア人職員・ミアさんを見つけた。 ほんの数分前、排泄介助のタイミングを間違えた彼女に対し、「何回言ったらわかるの?ちゃんとしてよ」と、少しきつめの口調で注意したばかりだった。
日本の現場ではよくあるやり取り。
でも、ミアさんにとっては、心が折れるほどの衝撃だった。
「叱る」は文化で大きく違う
ミアさんは、仕事に対して非常に真面目で、遅刻もなく、利用者にも丁寧な対応を心がけていた。 しかし、業務のスピードや判断にはまだ自信がなく、日々プレッシャーを感じながら働いていた。
そんな中での、先輩からの“強い叱責”。
彼女の目には、「怒鳴られた」と映り、
「自分はダメなんだ」「嫌われているのかも」と受け取ってしまった。
「指導」のつもりが、逆効果に
日本の現場では、注意や叱責は「育成の一環」として捉えられがちだ。
「ミスをしたらその場で伝える」「厳しさも必要」──その文化の中で育ってきた日本人職員にとって、それは当たり前の対応だった。
しかし、ミアさんのような背景を持つ外国人材にとって、
人前で強く言われることは「恥をかかされた」「人格を否定された」と感じるケースがある。
すれ違いを防ぐ“3つの視点”
1. 「伝えたいこと」を、感情と切り離す
注意すべきことは伝えるべきだが、
そのときの“語気”や“表情”が強すぎると、メッセージが届く前に心が閉ざされてしまう。
「あなたのことを思って言っている」という前置きも有効だ。
2. “叱責”ではなく“確認”の形で伝える
「なんでできなかったの?」ではなく、
「何か分かりづらいところがあった?」と問い直すことで、相手が話しやすくなり、改善点も明確になる。
3. フィードバックは「セット」
注意のあとに、必ず“フォローの言葉”を加えること。
「さっきは少しきつく言っちゃったけど、あなたの頑張りはちゃんと見てるよ」
「不安なときは、すぐに聞いてくれていいからね」
これだけで、相手の受け取り方は大きく変わる。
最後に:文化を理解することが“定着”への第一歩
「怒られたから辞めた」
「傷ついているようには見えなかった」
「日本語はできてるのに、なぜ伝わらない?」
そうした誤解の多くは、文化の違いを知らないことに起因している。
外国人材と共に働く現場には、「言葉」以上に「文化の翻訳」が必要だ。
その第一歩が、「叱り方」を見直すことかもしれない。
【インドネシア人材の「今」がわかる!】
当社のInstagramでは、来日予定の候補者の学習風景や、インドネシアの文化、日本語学校の様子などを日々発信しています。
▶ Instagramはこちら(@samasama_cw)
https://www.instagram.com/samasama_cw/
近年、介護施設で外国人材の活躍が当たり前になってきた一方で、 次のようなお悩みを耳にすることが増えています。
特定技能外国人支援コスト削減のご提案
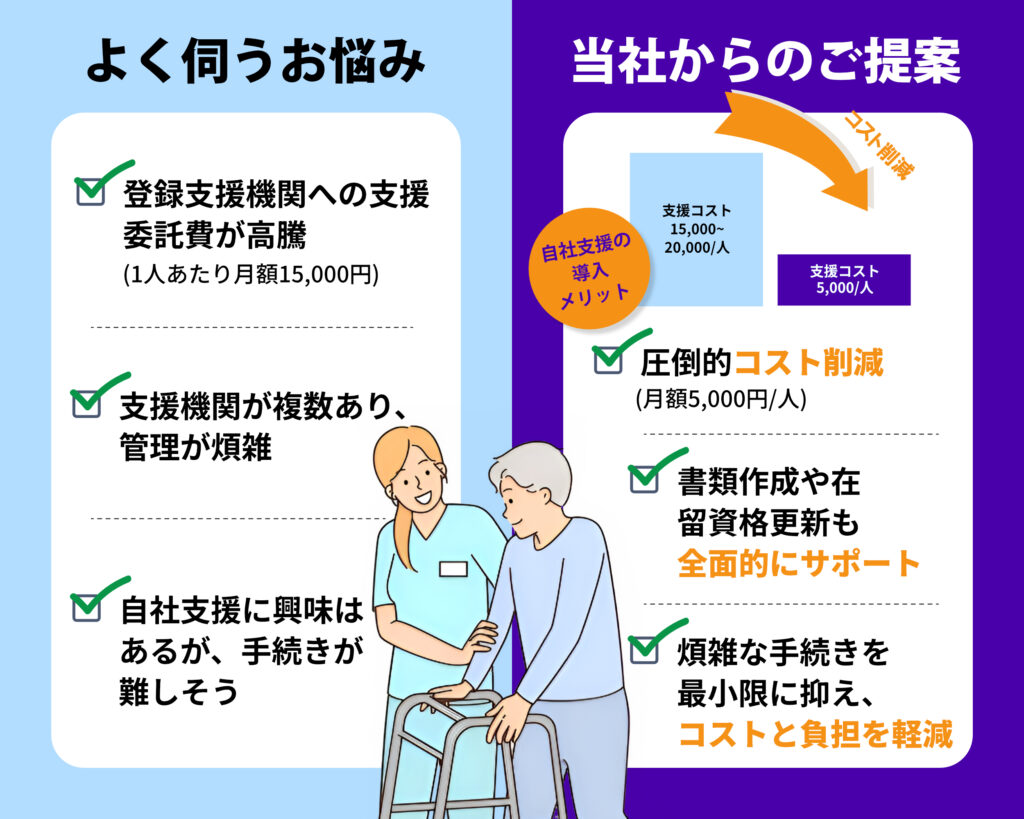
このようなお声に応え、当社では「自社支援」の導入をご提案しております。
まずは、削減効果のシミュレーションや導入事例をご紹介させてください。
オンラインでのご相談も可能です。
